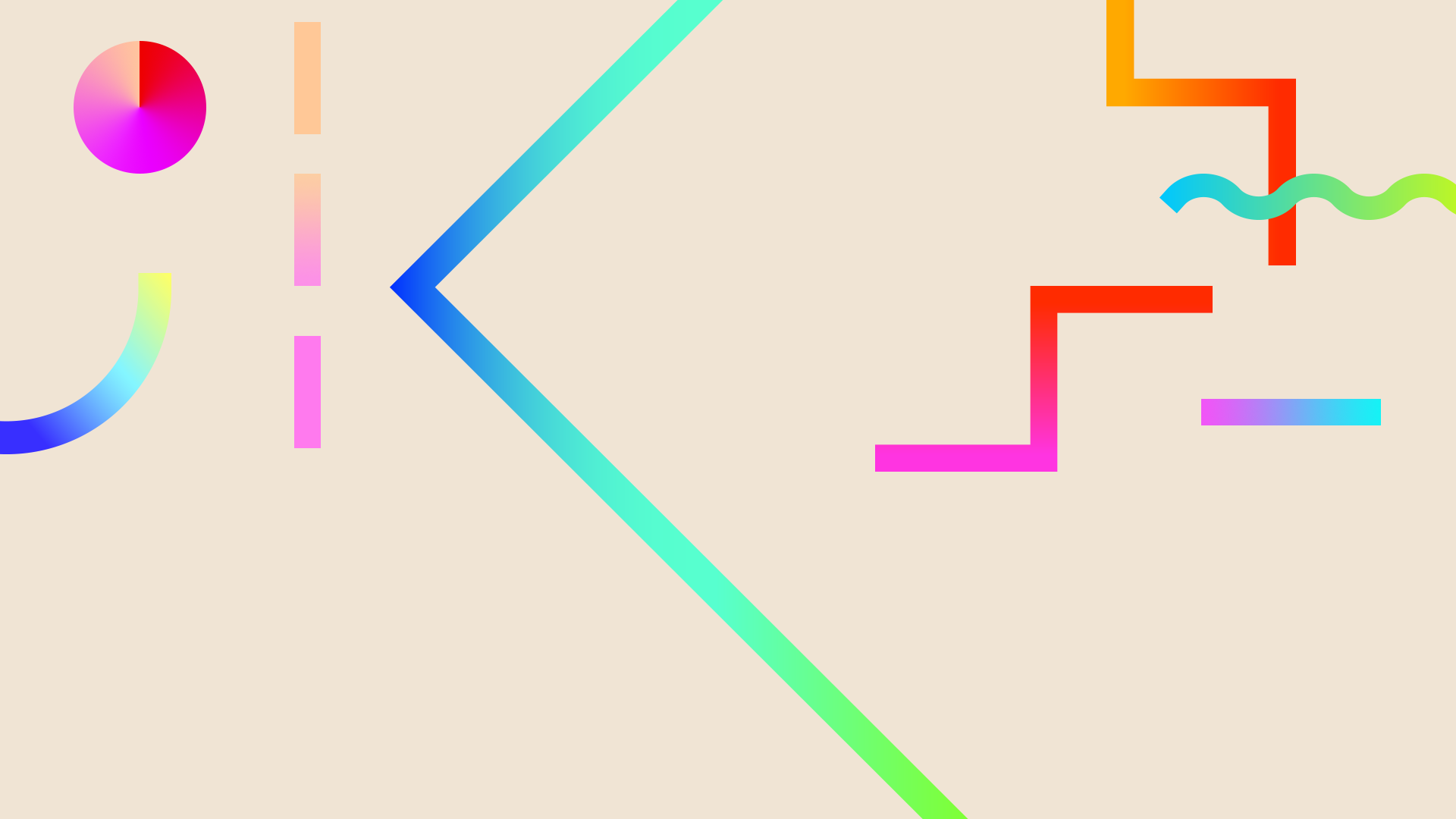検索
家で暮らすために歩く (40-20 )
- fairfax3939
- 2017年6月7日
- 読了時間: 2分


手すりはできるだけ長く、戸が閉まるギリギリまで。手すりと手すりの距離を短くするためです。
父の場合、歩行の安全のために手すりをつけるわけではありません。右麻痺の父が、動く左足を前に出すためには、その間その体重を受けてくれるものがなければ、足は一歩も前にでません。その役を左腕と杖が担ってくれていましたが、力が落ちて、杖では受けきれなくなりました。そこで、より体重をかけられる手すりで父の生活動線をつなぎました。つまり、手すりには全体重がかかる。壁の下地、手すりの受け具の位置、釘の長さなど、安全して使えるよう大工さんは充分考えてくれました。

加えて、壁と手すりの間隔は少し広く。これは、市販の受け具を使用した時、壁と手すりの間はほぼ4センチ。雲梯のように、腕を振り子のようにして手すりを持ち替える時、4センチでは指を壁にぶつけたり、指関節をこすったりしやすい。そこで、壁と受けの間に板をかませて、壁からの距離を広げ、指がすっとはいるようにしました。下の写真は手すりと手すりの距離が一番遠かった箇所。柱よりも手すりが長い。写真右、受け具には板がかませてあります。双方から1センチでも間を狭くしようとしました。

手すりは必要なところにつける。それが、普通つけない箇所でも。


こうした細やかな工夫があって、父は家で暮らすことができたのです。